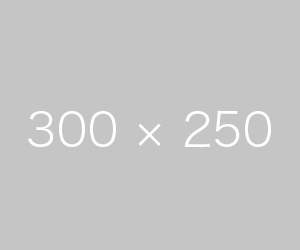-三つの窯元に”七つの質問”- 美濃焼産地で時代を意識しながらも自らのものづくりを全うするカネコ小兵、作山窯、深山の三つの窯元。その内なる想いを露わにするため、それぞれの代表に七つの質問を致しました。二つの質問には必ずお答え頂き、残りの五つは自由回答としてお話を伺いました。他社のスタッフがインタビュアーとなり、どの質問にどうお答え頂けるか?それぞれの窯元を想いをご覧ください。
-窯元情報-
・有限会社作山窯 https://www.sakuzan.co.jp/
・1987年(昭和62年)に作山窯を設立し2022年に創業35年を迎えた。
・創業者となる高井社長は設立年より現在まで代表職を担う。
・「美味しさを、美しさから」との想いのもと暮らしの楽しみとなる器づくりを行う。
・13種類の土とそれに調和する多様な釉薬と焼成方法。創業当時から手掛けられた数々のオリジナル製品。道具としての精度の高さややきものとしての完成度は大切にしつつも、拘泥することなく暮らしと調和する器を生み出す窯元。
(問一)『作山窯にとって欠かせないものは何ですか?』(語り手:作山窯 高井社長、聞き手:深山 柴田)
難しい質問ですね。外側から見たらうちの窯に欠かすことのない要素ってなんですか?

●質問者に問いかけながら想いを鮮明にする作山窯の高井社長
–要素と言われると分かりませんが、作山窯さんは明るい色合いのマット釉の優しい雰囲気の器の印象が強いですが、実はもっと土ものっぽい器など色んなラインナップがありますよね。でも、それだけ雰囲気が異なるのに全ての器から作山窯さんの個性を感じるんです。-
そういう意味では、どんな製品でもベースにあるのは【お料理が美味しく見えるように】かな。
–なるほど、腑に落ちますね。色んな種類の土を使っての器づくりは、たしかに“ものづくり”にはとてもこだわっていると感じますが、反面、素材への向き合い方は自由というか・・・私が勤務する深山だったら、素材は白磁に限定して、素材にこだわる事でものづくりの姿勢を表しますが、そう意味では、作山窯さんは特異ですよね。
ですね、基本的には直感で「あ、これ作りたい」からスタートするから、あまり素材や前提には固執しない「素材はこれじゃないといけない!」とか考えすぎると良くないと思ってて「こんな感じでいいんじゃない?」くらいの感覚で開発するね。

●(左)黒土で作られたスタイルシリーズ、(右)磁器土で作られたストライプシリーズ。參窯で紹介する二つの器だけでも異なる土で作られています。
-1987年の創業当時からそうした感覚で? –
創業して2年くらいは産地問屋さんからのOEMの仕事ばっかりだったよ。まずご飯を食べれるようになる事が大事だからね。その仕事をやりながら製品開発をしてた。
–第三回座談会(2021年6月頃開催*詳しくはこちらから)でうかがった梅花皮(かいらぎ)の製品が当時のものですか? –

●高井社長が手にする梅花皮の器は、深山の松崎社長がお気に入りとして持ち寄ったもの(第三回座談会にて)
梅花皮を手掛けたのは確か28才か29才頃に作ったから30年くらい前だね。作山窯をはじめて3年目くらいですね。梅花皮は本当に安定しない技法だから当時は産業の窯元ではどこもやってなくて、作山窯が一番最初に始めたんです。世の中に無いから凄く売れた。でも、その後、どんな経緯か分からないけど、その製造技法が産地内で流出して色んな窯元が生産をはじめましたね。
–その時はどうして梅花皮をやろうと思ったんですか?-
実際は狙って作ったというより、色んな試作をしてる中で偶然できたんです。でも、この雰囲気は良いなって感じて製品にしたんです。

●工場の片隅にならぶ試験用の釉薬。多様な素材と釉薬による試験から新たな表情が生まれる。
–梅花皮の器から現在まで作山窯さんの器は、その時代々々にフィットしているという印象ですが?-
いや、開発して発表したタイミングではあまりフィットしてないですよ。ほとんどは開発してから3~5年経たないと動き出さない。
–以前の座談会でも「我慢して出し続ける事だ」と仰ってましたね。ちなみに現在まで製品開発を続けられた中で、そうした直感的な開発スタイル変えてみようと思われたことはありますか?-
無いですね。それに製品自体はいっぱい変化してるからね(笑)。
–そういう意味では【高井社長の直感】も作山窯さんに欠かすことのできない要素ですね(笑)-
そうですね(笑)。次の記事に続く(2023年3月10日掲載)*毎週金曜掲載
-三つの窯元に”七つの質問”-回答一覧➡特設ページに戻る
■(問一)それぞれにとって欠かせないものは何ですか?への回答
「カネコ小兵にとって欠かせないものは何ですか?」
「作山窯にとって欠かせないものは何ですか?」
「深山にとって欠かすことができないものは何ですか?」
■(問二)へのそれぞれの窯元 の答えはコチラ
「伊藤社長(カネコ小兵)の記憶に残る出来事は何ですか?」
「高井社長(作山窯)の記憶に残る出来事は何ですか?」
「松崎社長(深山)の記憶に残る出来事は何ですか?」
■(その他の質問/最終話)へのそれぞれの窯元 の答えはコチラ
「カネコ小兵/前編-”産地の特性”と”窯元の個性”大切なのはどちら?-ほか」
「カネコ小兵/後編(最終話)-一緒に働きたいのはどんな人?-ほか」
「作山窯/前編-これからのやきものの生き残る可能性は?-ほか」
「作山窯/後編(最終話)-一緒に働いてみたいのはどんな人?-ほか」
「深山/前編-気になる自社製品は?その理由は?-他」
「深山/後編(最終話)-”産地の特性”と”窯元の個性”大切なのはどちら?-他」
■過去の座談会記事一覧
〉〉〉第六回座談会『他産地、他素材のものづくりに触れて-日進木工(高山市)-』アーカイブはこちらから
〉〉〉第五回座談会『野口さんとふりかえる2021年』アーカイブはこちらから
〉〉〉第四回座談会『美濃焼について思うこと』アーカイブはこちらから
〉〉〉第三回座談会『作り手の大切な器、我が家の食卓』アーカイブはこちらから
〉〉〉第二回座談会『作り手として感じる、それぞれの窯元の凄味』アーカイブはこちらから
・・・・・各窯元ウェブサイト・・・・・
參窯その1:カネコ小兵製陶所(岐阜県土岐市下石町)https://www.ko-hyo.com/
參窯その2:作山窯(岐阜県土岐市駄知町)http://www.sakuzan.co.jp/
參窯その3:深山(岐阜県瑞浪市稲津町)http://www.miyama-web.co.jp/
・・・・・參窯ミノウエバナシ contents・・・・・
●ブログ「三窯行えば、必ず我が師あり」三窯行えば-1.jpg) |
●オンラインストア「outstanding products store」ストア.jpg) |


相談所.jpg)
歓迎出張.jpg)